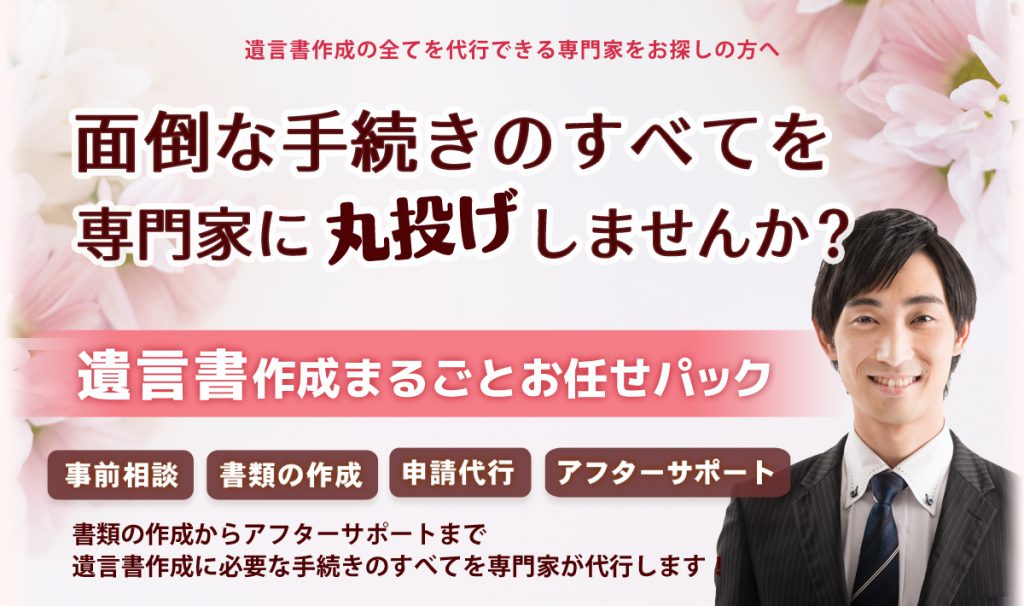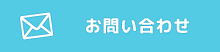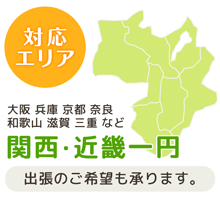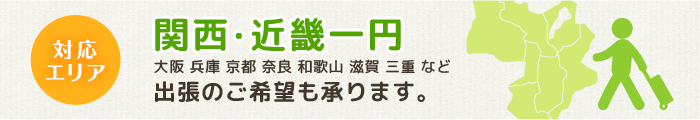遺言書でできること

インターネットの普及により、遺言書の重要性も随分と認知されてきました。ここ最近では遺言を書く人の割合がずいぶんと増えてきています。
遺言書があれば、残された家族の相続を軽減できたり、トラブルを防いだりと、いろいろなメリットがあるわけですが、法律に定められた形式で書かなければ無効とされる場合もあり、注意が必要です。

ここでは、遺言書によっていったいどんなことができるのか?ということを一緒に見ていきましょう。
未成年者後見人の指定
未成年者後見人は遺言で指定することができます。たとえば、「自分が死んだ後、あの人(元配者など)には親権は渡したくない」といった事情があるときには、遺言で未成年者後見人の指定をすることことで、親権が渡ることを阻止することができます。
相続分の指定と指定の委託
被相続人は相続人の相続分を定めることができます。
また、相続分を定めることを第三者に委託することもできます。
遺産分割の禁止
被相続人は、遺産分割を禁止することができます。ただし、相続開始の時から5年を超えない期間内に限定されます。
遺言執行者の指定と指定の委託
遺言者は遺言執行者を遺言で指定することができます。また、遺言者の指定を第三者に委託することもできます。
遺贈減殺方法の指定
遺留分を侵害する遺贈が複数あるときは、遺贈の額に応じて減殺することができますが、遺言者は減殺の順序や割合について、遺言で異なる意思表示をすることができます。
相続人の廃除・取り消し
遺言で相続人の廃除を意思表示することができます。また、排除の取り消しも遺言で行うことができます。
未成年者後見監督人の指定
未成年者後見監督人は、未成年後見人を管理する人のことで、遺言で指定することもできます。
遺産分割の方法の指定と指定の委託
被相続人は分割の方法を遺言で指定することができます。
また、分割の方法を指定することを第三者に委託することもできます。
遺産分割における共同相続人の担保責任の定め
共同相続人の誰かが受け取った遺産に瑕疵があった場合、お互いの損害を担保する必要があります。
また、被相続人は、この共同相続人の担保の定めをすることができます。
遺贈
財産を遺言によって無償譲与することを遺贈といいます。
持戻しの免除
特別受益の持ち戻しを免除することを、遺言書で意思表示することができます。遺贈の持ち戻し免除の意思表示は、遺言でのみすることができます。
子の認知
遺言で子の認知をすることができます.
遺言書でできることをもっと知りたいなら?
ご本人の状況によって、何通りもの遺言書の活用方法があります。まずは遺言の専門家を交えて無料相談してみませんか?遺言書に関する無料相談フォームはこちらをご覧ください。→https://yuigon.korenikimari.com/will/omakase/